退職金に関する記事は「退職金は勤務年数が3年未満では基本的に支給されない」の中で解説しているので、退職金に関してこれ以上細かく説明する必要ないと思いますが、退職金を受け取る際にかかる税金に関して少しだけ解説していきます。
退職金にも課税される
会社を退職した時に支給される退職金ですが、退職金にも税金が課税されるって皆さんご存知でしたか?
ちなみに、税金とは所得税と住民税なのである・・・
結論から言えば、毎月の給料や賞与の様に支給額に対してガッサリ持っていかれることはありませんが、計算方法が少々面倒なのと、キチンと手続きをしなければ多く徴収される可能性があるので、この記事を見て理解しておいて下さい。
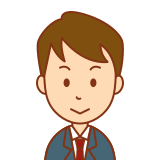
計算は会社が勝手にしてくれるのでそれほど気にする必要はありませんが・・・
どれぐらい優遇されるの?
| 勤続年数 | 控除額 |
|---|---|
| 20年まで | 40万円×勤続年数 ※80万円が下限 |
| 20年~ | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
ここで算出された課税対象額から更に1/2が控除されます。
文章で書くと分かりにくいので、例を挙げてみましょう。
例
勤続年数が32年のおっさんが2,000万円の退職金を支給された場合
勤続年数が20年を超えているので、
2,000万円-(800万円+70万円×(32-20年))
=360万円
そこから更に1/2が控除されるので、
360万円/2
=180万円が課税対象になります。
180万円の所得税は5%で住民税は10%になるので、
所得税は9万円、住民税は18万円
になります。
収入の割にかなり安いですよね・・・
優遇措置を受けるには「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければいけない
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務している会社に提出しなければ退職金にかかる税金の優遇措置を受けることができませんので注意して下さい。
退職所得の受給に関する申告書は会社で保管されているので貰って下さい。また、税務署でも貰えるし国税庁のホームページからでもダウンロードできます。
優遇措置が無いとどうなるの?
優遇措置が無ければ、退職金の20%が源泉徴収されてしまいます。要は払い過ぎですね。
払い過ぎた税金は確定申告をすれば取り返すことは可能ですが、手続きが面倒だし、払い戻されるのにも時間がかかるので、出来れば優遇措置を受けてスムーズに退職金を受け取った方が楽チンです。
- 退職金には優遇措置がある
- 優遇措置を受けるには「退職所得の受給に関する申告書」が必要
- 払い過ぎた分は確定申告で取り返す

